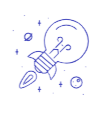回答: 宿題のアイデアは、宿題の発明者として知られるイタリアの教育者ロベルト ネビリスによって広められました。
宿題の起源は明らかではありませんが、歴史を通じてさまざまな形で生徒に課せられてきたと考えられます。しかし、学生が完了する定期的な授業外の課題としての宿題という現代の概念は、19 世紀後半の米国にまで遡ることができます。
宿題の目的は次のとおりです。
- 授業内容の理解を強化し、深める
- 自主的な学習と批判的思考を促進する
- 今後のレッスンや試験に備えて生徒を準備する
- 学習習慣と時間管理スキルを身につける
- 生徒が学んだことを応用し実践する機会を提供します。
宿題の特徴は次のとおりです。
- 教室での学習を強化するために教師によって割り当てられます
- 通常は通常の授業時間外に完了します
- 個人またはグループでの作業が可能
- 書く、読む、問題解決、研究などのさまざまなタスクが含まれる場合があります
- 多くの場合、生徒の全体的な学業成績の一部として採点または評価されます。
宿題に関する研究や記事は数多くあり、宿題の有効性、生徒の幸福への影響、宿題の割り当てと完了へのアプローチなど、さまざまな側面が取り上げられています。関連リソースには次のようなものがあります。
- 全米教育協会の宿題に関する推奨事項では、一晩あたり各学年ごとに最大 10 分の宿題を推奨しています。
- ハリス・クーパーらによるメタ分析「宿題と学力の関係: 研究の総合」(1987-2003) では、特に年長の生徒において、宿題と生徒の学力の間に正の相関があることが判明しています。
- サラ・ベネットとナンシー・カリッシュによる記事「宿題が多すぎると子供に悪い」では、過剰な宿題は生徒の健康、福祉、家庭生活に悪影響を与える可能性があると主張しています。
- アルフィー・コーン著『宿題の神話: なぜ私たちの子供たちは悪いことをしすぎるのか』という本は、宿題をめぐる思い込みや実践を批判し、代替案を提案しています。
試験と評価の実践を改善するための今後の方法は次のとおりです。
- プロジェクト、プレゼンテーション、パフォーマンス課題などのさまざまな評価方法を取り入れて、学生の知識とスキルをより適切に評価します
- 生徒の学習をサポートするために、タイムリーかつ詳細なフィードバックを生徒に提供します
- オープンブックまたはオープンノートの試験を許可することで、学生がリソースを活用し、知識を応用することが奨励されます。
- オンラインテストや自動採点など、テクノロジーを活用した評価を導入して効率性と公平性を高める
- クイズや進捗チェックなどの形成的な評価を組み込んで、生徒の学習を継続的に評価します。たとえば、学校では、歴史コースでの生徒の学習を評価するために、従来の試験、クラス プロジェクト、内省課題を組み合わせて使用する場合があります。