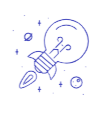R には、出力を印刷するためのさまざまな方法があります。 R プログラムで出力を印刷する最も一般的な方法には、と呼ばれる関数があります。 プリント() 使用されている。また、R のプログラムを上書きすると、 コンソール 1 行ずつ出力すると、出力は通常どおり印刷され、その出力を印刷するために関数を使用する必要はありません。これを行うには、出力変数を選択して を押すだけです。 走る ボタン。 例:
R
# select 'x' and then press 'run' button> # it will print 'techcodeview.com' on the console> x <- 'techcodeview.com'> x> |
>
>
出力:
[1] 'techcodeview.com'>

を使用して出力を印刷します プリント() 関数
使用する プリント() 出力を印刷する関数は、R で最も一般的なメソッドです。このメソッドの実装は非常に簡単です。
構文: print(任意の文字列) または print(変数)
例:
R
Javaのループの終了
# R program to illustrate> # printing output of an R program> # print string> print>('GFG')> # print variable> # it will print 'techcodeview.com' on the console> x <- 'techcodeview.com'> print>(x)> |
Javaの文字列から置換する
>
>
出力:
[1] 'GFG' [1] 'techcodeview.com'>
を使用して出力を印刷します ペースト() 内部の機能 プリント() 関数
R はメソッドを提供します ペースト() 文字列と変数を一緒に含む出力を印刷します。このメソッドは内部で定義されています プリント() 関数。 ペースト() 引数を文字列に変換します。使用することもできます ペースト0() 方法。
注記: past() と past0() の違いは、引数 sep がデフォルトで (paste) と (paste0) であることです。
構文: print(paste(任意の文字列、変数)) または、print(paste0(変数、任意の文字列))
例:
R
# R program to illustrate> # printing output of an R program> x <- 'techcodeview.com'> # using paste inside print()> print>(>paste>(x, 'is>best>(paste inside>print>())'))> # using paste0 inside print()> print>(>paste0>(x, 'is>best>(paste0 inside>print>())'))> |
>
>
出力:
[1] 'techcodeview.com is best (paste inside print())' [1] 'techcodeview.comis best (paste0 inside print())'>
を使用して出力を印刷します スプリントf() 関数
スプリントf() 基本的には Cライブラリ 関数。この関数は文字列を次のように出力するために使用されます。 C言語 。これは、次のように値と文字列を一緒に出力するラッパー関数として機能します。 C言語。 この関数は、出力する string と変数の書式設定された組み合わせを含む文字ベクトルを返します。
構文: sprintf(任意の文字列 %d、変数) または、sprintf(任意の文字列 %s、変数) または、sprintf(任意の文字列 %f、変数)) など。
例:
ラテックステーブル
R
# R program to illustrate> # printing output of an R program> x = 'techcodeview.com'># string> x1 = 255># integer> x2 = 23.14># float> # string print> sprintf>('%s is best', x)> # integer print> sprintf>('%d is integer', x1)> # float print> sprintf>('%f is float', x2)> |
>
>
出力:
>sprintf('%s が最適です', x) [1] 'techcodeview.com が最適です'> sprintf('%d は整数です', x1) [1] '255 は整数です'> sprintf('%f は float です', x2) [1] '23.140000 は float です'> を使用して出力を印刷します 猫() 関数
R で出力を印刷するもう 1 つの方法は、cat() 関数を使用することです。それと同じです プリント() 関数。 猫() 引数を文字列に変換します。これは、ユーザー定義関数の出力を印刷する場合に便利です。
構文: cat(任意の文字列) または、cat(任意の文字列、変数)
例:
R
# R program to illustrate> # printing output of an R program> # print string with variable> # '
' for new line> x = 'techcodeview.com'> cat>(x, 'is best
')> # print normal string> cat>('This is R language')> |
>
>
mylivecricket ライブクリケットに参加します
出力:
techcodeview.com is best This is R language>
を使用して出力を印刷します メッセージ() 関数
R で何かを出力する別の方法: メッセージ() 関数。これは印刷出力には使用されませんが、プログラム内の警告やエラーではない単純な診断メッセージを表示するために使用されます。ただし、印刷出力などの通常の用途には使用できます。
構文: メッセージ(任意の文字列) または、メッセージ(任意の文字列、変数)
例:
R
# R program to illustrate> # printing output of an R program> x = 'techcodeview.com'> # print string with variable> message>(x, 'is best')> # print normal string> message>('This is R language')> |
>
>
出力:
techcodeview.com is best This is R language>
出力をファイルに書き込む
変数の値を含むファイルを印刷または書き込むには、と呼ばれる関数があります。 書く() 。この機能は、と呼ばれるオプションで使用されます テーブル ファイルを書き込むために。
構文: write.table(変数、ファイル = file1.txt) または、write.table(任意の文字列、ファイル = file1.txt)
例:
R
ラドヤード・キプリングの言葉を言い換えると
# R program to illustrate> # printing output of an R program> x = 'techcodeview.com'> # write variable> write.table>(x, file = 'my_data1.txt')> # write normal string> write.table>('GFG is best', file = 'my_data2.txt')> |
>
>
出力: